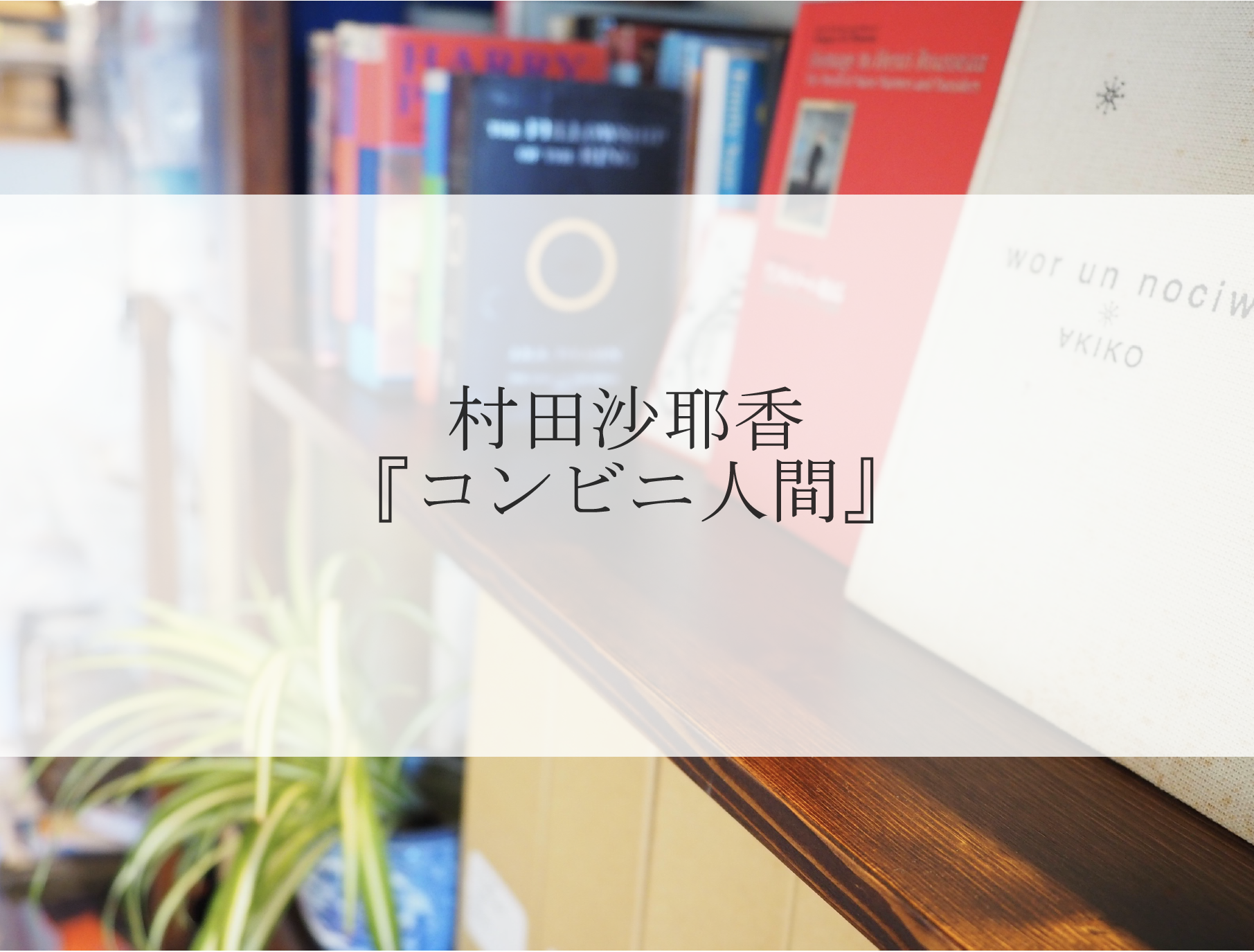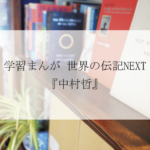久々になんの目的もなく、小説を読みました。
いつか話題だったからというだけで、「読む本リスト」に入れていた作品です。
予想のナナメ上、抜群に面白かったですね。
題:『コンビニ人間』
著者:村田 沙耶香
初版:文藝春秋 2016年
コンビニに居場所を求める現代人の話かと構えていたら、そうなんだけど、そうじゃなかったのです。
タイトルは無機質な近代生活の比喩かと思いきや、本当に文字どおり、コンビニ人間の話でした。
コンビニ教徒、いやコンビニ星人とでもいうか。
主人公の生い立ち、思考回路、常人離れした言語センス。
マイノリティに親しい読者ならば、これは……、と序盤で正体に気づくでしょう。
まわりに馴染めない主人公にとって、「回転し続ける、ゆるぎない正常な世界」としてのコンビニは信頼すべき光の箱、入り口のチャイムは救済の鐘となります。
さてそこから、お決まりの「理解のある彼クン」が現れてつまらなくなる展開を恐れていましたが、この作品ではTwitterから這い出した妖怪のような男が登場するものの、最後までしっかり面白いままで、コーンの先までちゃんと詰まったアイスクリームみたいに満足しました。
なおラストは、ハッピーエンドともバッドエンドとも捉えられるだとか、バッドエンドだとかいう解釈があるようで、個人的にはぎょっとしました。
私が考えるかぎり、ザ・ハッピーエンドの一択です。
すっかり気に入ったので、読み終わってすぐ冒頭から再読。
続けざまに二度読んでしまうなんて。
おかげで頭の中にはコンビニの音が鳴り響き、だいぶいかれてきました。
多くの読者にとって、この主人公は不可解で、不愉快ですらあるかもしれません。
そこで先に、ドナ・ウィリアムズによる1992年の名著『NOBODY NOWHERE』(邦題『自閉症だったわたしへ』)を読んでおくと、解像度の次元が変わります。
こちらはノンフィクションのシリアスな自伝なのですが、履修することで、くだんの小説も「あ、これ進研ゼミで見たやつだ」という具合になるでしょう。
また、ブラックユーモアの味わいは、カレー沢薫さんの生活系コラムやエッセイ漫画を読み漁ってきた人に受けるのではないかと。
違うといえば全然違うのですが、私の中のアルゴリズムが直感で「これを読んだ人にはこちらもおすすめ」に挙げてきます。
『なおりはしないが、ましになる』とか「カレー沢薫のほがらか家庭生活」あたりですかね。
『コンビニ人間』では、「どうすれば『治る』のかしらね」という台詞の「治る」がキーフレーズのひとつでもあります。
もし現実ならば、そばにいる人が「治してもらおうよ、もうそれしかないよ」「お願いだから、普通になってよ」(P.131)と泣く気持ちが、私には痛いほどわかります。
一方で、この社会は案外さまざまな星の宇宙人が「普通の人」に擬態して紛れ混んでいるようなものです。
出身星は異なれど、世を渡る擬態星人たちにはどこか共感する部分があるのではないでしょうか。
そして、ある面においては、多数派の「自分を変じゃないと思っている人たち」にも、生きる悩みの普遍性を感じられるのではないでしょうか。