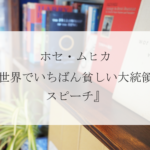2025年3月現在、『人間を考える「旅に学ぶ」』と題する5回シリーズが、NHKカルチャーラジオで放送されています。
第1回の講師は、『地球の歩き方』社長 新井邦弘さんです。
そこで、ラジオで拝聴した新井さんのお話をもとに、旅学ゼミとして自由に語り合う会をひらきました。
放送概要
1979年に創刊されて以来、多くの旅行ファンに愛されてきた海外旅行ガイドブック『地球の歩き方』。その代表である新井邦弘さんは、日本人のパスポート取得率が17%にまで落ち込んでいる点を危惧します。海外体験の重要性は「行動変容」「不便益」(ふべんえき)の二つのキーワードにあるといいます。そして、予定外の情報の洪水に24時間さらされ続け、五感を刺激されることこそが、海外旅行のだいご味であると語ります。
(番組サイトより引用)
人間を考える「旅に学ぶ」(1)
『地球の歩き方』社長 新井邦弘さん
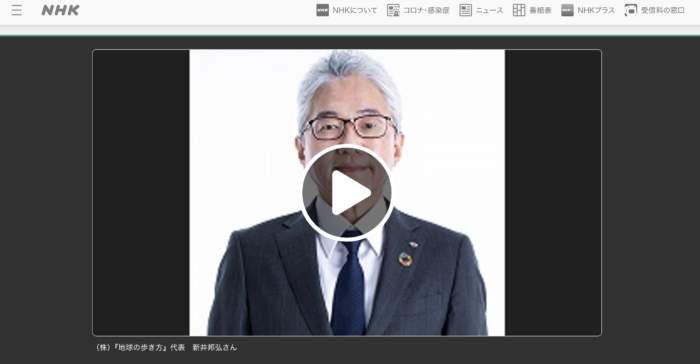
NHKカルチャーラジオ(日曜カルチャー)
ラジオ第2 毎週日曜 午後8時
初回放送日:2025年3月2日
聴き逃し配信:2025年4月27日 午後9:00配信終了
https://www.nhk.jp/p/rs/GPV3P86GMP/episode/re/N7547R9Z7K/
『人間を考える「旅に学ぶ」』を語る会(1)
五郎:会社員。元・青年海外協力隊員。
halkof:当サイト運営者。ライター/旅学研究家。

ラジオ 人間を考える「旅に学ぶ」第1回、総じて、完全同意!と感じるお話でしたね。

「分かる」という感想ですね。私はちょうど新井さんの次の世代くらい、旅をしたのは1990年代の1ドル100円を切る時代でしたけど、やっぱり『地球の歩き方』を持って、格安航空券を取って行きましたから。旅先では上の世代の武勇伝もよく聞いていたし。中国はビザを取るのが大変だったから、香港から中国へ入るのが王道ルートだったんですよね。私は船で上海に入ったんですけど、町から出るのに列車の切符を取るのが一苦労で。1

私が中国に行った2000年代も、列車の切符を取るのは大変でしたね。行列した窓口で「メイヨー(有りません)、メイヨー」と断られて(笑)。

お話に出た、NHKドキュメンタリー「シルクロード」にも憧れていましたしね。中国編の『地球の歩き方』を買いに行ったとき、隣りにシルクロード編の『歩き方』もあったので一緒に買ったんですよ。それでウイグル自治区のカシュガルまで行こうとしたら、手に入ったのは3日後のバスの切符で、予定外の町で3日待つことになって(笑)。観光地ではない、アクスという町でしたけど、地元の人はみんな朝からまじめに働いていたので、旅人としては居場所のなさを感じました。

あるある(笑)。シルクロードで喜多郎2を聴く旅は、2000年代でも健在でしたよ〜。

では、「旅に学ぶ」というテーマについて、新井さんのお話に「行動変容」というキーワードが出てきましたが、いかがですか? 行動変容しました?

そうですね、誰の言葉だったかな、「行動変容をもたらさないことはバーチャルに過ぎない」という意見を思い出しました。やっぱり「現地で、四六時中逃げられないなかで、五感に刺激を受けつづける」というのは、行動変容が起きる可能性が高いですよね。バーチャル旅行で得られるのは視聴覚だけですけど、現場では自分の肌で、匂いで、味でも、感じるわけですもんね。

空気、匂い、味もねえ。総合的な刺激って大きいですよね。

行動変容というか、価値観の軸が変わるという意味では、私はカシュガルまで行って、「こんな西の果てまで来ても、人間やってることは一緒だな」と思いましたよ。星空があって、人間がメシ食って、泣いたり笑ったりしている。それに、ウイグル人は彫りの深い顔立ちですから、慣れないうちは少し怖い気もしたんですけど、接してみるとウイグルの人たちって本当に優しい! 見た目の違いは関係ないんだと、先入観が覆りました。

そうですよねえ。ラジオではイランのお話がありましたけど、イスラムの国々とかも、実際に行ったことがある人とない人では、イメージが変わりますよね。アメリカの911事件後とか、ニュースの見方が全然違ったと思います。
私はキューバに行ったとき、感じました。日本ではメディアがアメリカ寄りで、キューバって悪の独裁国みたいに報道されがちですし、一方では、キューバは有機農業100%で医療・教育無料のパラダイス、みたいな言説もある。実際はどうなのか、自分の目で見て、肌で感じていくと、メディアを鵜呑みにしないように、解釈や行動が変わってきますよね。

キューバって、行った人からはみんな「良かった」って聞きますね。
やっぱり頭の中で分かっているのと、実際に感じるのは違いますよね。解像度が上がります。私はアメリカに行ったとき、ハリウッド映画みたいに銃声は聞こえないな、と思いました(笑)。

ラジオではもうひとつ、「不便益」というキーワードがありましたが、こちらについてはいかがですか?

ああ、不便益と便益の間で、ガイドブックは紙がいいのか、デジタルがいいのか、自分は答えが出ません。「寄り道」というのも大事なキーワードですよね。紙メディアのほうが、ぱらぱらめくって、関係ないところを読んだりして、寄り道があるかな。旅先で暇なとき、行かない町のページもひらいて読んでみたりね。

私の場合は、紙よりウェブのほうが寄り道しちゃうかも。ずっとサーフィンしちゃって、キリがないです(笑)。旅先で暇なときも、インターネット見ちゃいますしね。
でも、ウェブで予約できるのは便利なのかといったら、そうでもないと思うんです。結局、ウェブで探して予約しないと宿に泊まれないから、旅先でも明日の宿を予約するために延々とスマホをいじってるんですよ。予約サイトって、星の数とかクチコミとか、判断材料と選択肢がありすぎるがゆえに、良さそうな宿を探してずっとクチコミを読み続けてしまう。ウェブ予約なんてない時代に、安宿街で片っ端から「部屋見せて」とあたっていって、その場で今夜の宿を決めるほうがよっぽど簡単でした。

ウェブ予約の便益って、宿側の便益かもしれませんね。
それから、ウェブがなければ、音信不通になる、という不便益もありますよね。あと、旅では日本語が通じない不便益も。

日本語が通じない不便益って重要ですよね。たとえば台湾や韓国はとても良いところでみんな大好きな旅行先ですけど、文化的に近いし、わりと日本語が通じちゃったりします。隣国へ行くのはとても大切だけれど、日本語がまったく通じないような、全然違った遠い外国へ行くのもまた大事ですよね。

それからラジオでは、「単なるレジャーやワクワクドキドキだけじゃなく、それ以上のことを持ち帰ってほしい」というお話もありましたね。

それ以上のことで、グローバル人材の育成とか、日本を訪れる外国人旅行者に親切に接する、寛容な精神を身につけていくという点では、旅に出て海外体験するのももちろんですけど、国内でもできることがあるんじゃないかと思いました。学校で教えるとか。

国際理解教育とか、多文化教育とかですね。最近は、小学校から実施しているところもあるんじゃないでしょうか?


私は旅行業界で働いていましたが、どの国も通常はインバウンドを増やそうとするなかで、日本はアウトバウンドが少なすぎて、出国者数の増加をめざしている異例な国だといわれていましたね。ラジオで新井さんも、特に若者に海外体験はマスト、海外渡航率をどう回復するか真剣に考えなくては、とおっしゃっていました。
ただ、それなりのお金と暇と将来への希望があれば、若者も海外に発つと思うんですよ。今の学生は、学費や生活費を稼ぐのに精一杯だったり、長期休暇も就活とインターンシップで埋まったり、お金も時間も厳しい。それから卒業して就職しても、きちんとお給料や休暇が得られるように、『地球の歩き方』の社長さんにはぜひ経済界への働きかけをお願いしたいです。

経営者という面では、ラジオのお話で、ガイドブック出版の行く末を模索されているんだなあという印象も受けました。まあそういう自分も、モロッコに行ったとき『地球の歩き方』を飛行機に置き忘れちゃったんですけど、ガイドブックがなくてもなんとかなったのは事実……。
それでもガイドブックが頼りになるのは、トラブルがあったときですよね。警察や病院の情報とか。

たしかに、私も『地球の歩き方』で絶対に読むのは危機情報、トラブルや詐欺の事例ですね!

あとは、情報がうさんくさいのが初期の『歩き方』の良さ、面白さでしたけど、最近はそうでもなくなりました。

ああ、うさんくささは面白さですよね(笑)。今はネット情報のほうがうさんくさいから面白いのかもしれませんね。

『ニッポンの海外旅行』(山口誠 著)6で論じられていたように、草創期の『歩き方』はうさんくささを含むクチコミを前提として面白く読まれていたのが、現在の読者はそうではなくて、正確な情報を前提に求めるようになっているんでしょうね。

本当に、『ニッポンの海外旅行』で述べられていたとおりですよね。
いずれにしても、ガイドブックにはひととおりの概要がまとまっていますから。今後、私は旅先に紙のガイドブックを持って行くことはもうないでしょうけれど、事前に家で目を通すとは思います。

紙のガイドブックを持って、スマートじゃない旅ができるのは、今が最後のチャンスなのかもしれませんね。
- ラジオ内での「初めての海外で中国に行って、ドアのないトイレや大混雑の列車にカルチャーショックを受けた」という新井さんのお話にちなんで。 ↩︎
- 喜多郎:喜多郎作曲のNHK特集「シルクロード」テーマ曲。 ↩︎
- ギャップイヤー(gap year):学校卒業と入学の間、卒業と就職の間などにもうけた、多様な社会体験を積むための猶予期間。イギリス発祥で欧米に浸透しており、外国への長旅やボランティアをする人が多い。 ↩︎
- グランドツアー(grand tour):18世紀頃イギリス上流階級の子弟たちが教養を深めるためにヨーロッパを周遊した教育旅行。 ↩︎
- トビタテ!留学JAPAN:文部科学省が2013年に開始した留学促進キャンペーン。2025年現在は産官学で奨学金を支給。https://tobitate-mext.jasso.go.jp/ ↩︎
- 『ニッポンの海外旅行 ―若者と観光メディアの50年史』山口誠 著、ちくま新書、2010年 ↩︎
レビューシート
五郎:
今、旅をする意味とは。今こそ旅する意義とは。旅に出るなら今でしょ、という理由とは。今更旅立つ動機は。今しか出来ない旅とは。
講義にインスパイアされて、付け加える事は無いかと自分なりに考えてみました。放送の内容とはあまり関係ありませんが。
現在は旅のIT化の過渡期の最中、もしかしたら最終段階直前なので、変化の時期をしっかり経験して置く事には一定の意義が有ると思います。時代の目撃者になる、というと大袈裟ですが。
紙のガイドブックのみで、携帯電話無し、ネット予約なしで旅ができる時代は、もうじき終わるかも知れません。古い世代の旅人にとっては、慣れ親しんだ流儀で旅をできる時期は、残り少ないかも知れないのです。
反対に、最新流行のスマートなスタイルで旅をしておくのも、今だけしか出来ない経験かも知れません。すぐに陳腐化して、次の何かに取って代わられるでしょうから。ウユニ塩湖でインスタ映えしてる人はまだいるのでしょうか。また、AIに手を引かれて旅する時代が、まもなくやって来るでしょうから、主体的に旅することも無くなるかも知れません。2025年頃の旅が、将来振り返った時にどう評価されるのかはわかりませんが、リアルタイムで実践できるのは今だけでしょう。
ポストコロナ、ウィズコロナ、あるいはパンデミックとパンデミックの間の小休止になるかも知れない、という意味でも未来は分りません。いつでも行けると思っていた場所に行けなくなるかも知れません。行けずに後悔しそうなら、行ける時に行っておく、というのも一つの考え方でしょう。
と言いつつ、私自身がそういう旅をしたのは、返還前の香港&マカオ程度ですが。
halkof:
旅の学びは「行動変容」と「不便益」にある。同感でした。講演を拝聴し、手元のメモには「0(ゼロ)が1(イチ)になる飛躍」「その国の人と会ったことがある、喋ったことがある、という経験」「体験と照らし合わせる批判精神の形成」「旅はそのトリガー」といった言葉が書き留めてあります。やはりこうした点で、海外への旅が重要だと思います。
ただ、「だったら金をくれ」「休みをくれ」というのが多くの人の本音ではないでしょうか?
右肩上がりの豊かな時代と違い、奨学金の返済にも苦しむ現代で、海外放浪を楽しむ余裕のある若者はどれほどいるのでしょう。そもそも学生は就活が忙しくて、旅どころか授業にさえ出られない状況です。
そこでまず私が提言したいのは、
・就活時期の繰り下げ
・新卒一斉採用の廃止
・ギャップイヤー、サバティカルイヤーの導入
・休暇の分散化
です。
旅ができる社会作りとしては、江戸時代の伊勢参りにも倣いたいところです。
「かわいい子には旅をさせよ」という当時の格言は、あらためて見直す価値があると思いました。
旅学ゼミ、今後も不定期開催です!